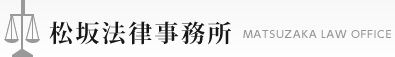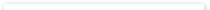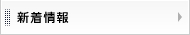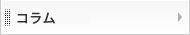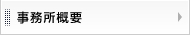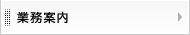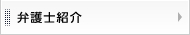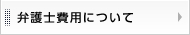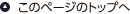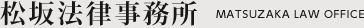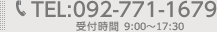- ホーム >
- コラム
| 2017/09/13 | 弁護士松坂徹也のコラム(26)「読書の歓び-第156回直木賞-」 |
読書の歓び ―第156回直木賞― 私は小説を読むのが楽しみで、いつもカバンの中に文庫本をひそませ移動中や空き時間があったりするときなどに取り出して読んでいます。 作家は小説を書くにあたってはその題材について事前に十分に調査取材をします。関係する文献や記録を読んだり又舞台となる現地に臨んだりもします。その方法やそれにかける時間は作家によって違いがありますが、膨大な時間をかける人もいます。 「ポーツマスの旗」「破獄」「ふぉん・しいほるとの娘」「桜田門外ノ変」「戦艦武蔵」「関東大震災」等を書いた吉村昭の作品は記録文学と言われ、事前の調査取材は質量ともに大変なものだったそうです。戦艦武蔵は長崎の三菱重工業で作られましたし、シーボルトの娘、イネは長崎で生まれ育ちましたから、これら小説を書くために長崎を訪れた回数は相当なものだったようです。そのあたりのことは氏の妻津村節子が書いた「紅梅」という吉村昭の闘病生活を描いた小説(菊池寛賞受賞)に書かれています。因みに吉村昭は自身の弟の闘病を描いた「冷たい夏、熱い夏」という小説で毎日芸術賞を受賞しています。 このように小説には作家の思いとともに小説の背景にあるものの調査取材をした貴重な事実が示されています。先頃亡くなられた林えいだいさん、この方は記録作家と言われていています。氏が残した多くの作品(朝鮮半島出身者の強制徴用や太平洋戦争をあつかったものが多い)には氏の入魂の調査や取材が作品の基となっています。小説を読むとその度に「知」や「情」の小部屋が満たされるわけでそこに大きな歓びを感じます。 最近「また、桜の国で」という須賀しのぶの小説を読みました。舞台はポーランド、時代は第二次世界大戦が始まる少し前から終戦直前までです。そしてここには日本人の外交官も登場し、ポーランドのために働きます。 私達は第二次世界大戦と言えば中国や南方を舞台とする太平洋戦争のことを中心に考え、ヨーロッパ戦線のことについてはナチスのユダヤ人虐殺以外にはあまり考えませんし、知識もそれほど深くはありません。 しかし、この小説は第二次世界大戦のさなか、ポーランドという国がどのようにナチスドイツから攻撃を受けたか、周辺の大国にいかにほんろうされたかを示しています。ポーランドはそれ以前からソ連やドイツの支配がくりかえされ、一時は国それ自体あるいは国民の主権さえ奪われていたわけでこの小説はこのことにも触れています。 ポーランドは常に近くの大国の支配に苦しめられてきましたが、それでも国民は自分たちのアイデンティティを失うことなく強く生きていきます。それを支えたのはショパンの音楽でした。国が苦境に立たされたときは戦火のなかでもラジオでショパンのピアノ曲を流し国民を勇気づけたのでした。音楽の力はすごいですね。 第二次世界大戦の終わりにより、ナチスドイツによって酷い目にあったポーランドは解放されることになりますがその後がいけません。次はソ連による支配と自由の剥奪です。小説には出てきませんがこのソ連支配の間もポーランド人は長い苦しい時代を耐えたのでしょう。 しかし、今は冷戦の終結により平和な時を迎えています。ポーランドの人こそ平和の意味や大切さを、身をもって感じているのではないでしょうか。 私はこの「また、桜の国で」に深い感銘を受けていましたが、この小説は2016年第156回直木賞(正確には直木三十五賞です)の候補となりましたが残念ながら逃しました。このとき直木賞の栄誉に輝いたのは恩田陸の「蜜蜂と遠雷」です。 一昔前、芥川賞は純文学、直木賞は大衆文学と言われていましたが現在では直木賞の対象作品も純文学です。あえて両賞を区分けするとすれば芥川賞は新人の登龍門、直木賞はすでに実績のある作家のなかで特にすぐれた作品に対する賞ということになるでしょう。 因みにミステリーやハードボイルドと言われる作品も十分に純文学で、高村薫、及南アサ、小池真理子、藤田宜永などはもとはといえばミステリー作家ですし、大沢在昌や宮部みゆき、北方謙三、東野圭吾の作品の文学性は非常に高いものです。 そこで「蜜蜂と遠雷」をすぐに読みました。舞台は東海地方の都市での国際ピアノコンクールです。(コンクールの名称は「芳ヶ江国際ピアノコンクール」となっていますが、先日亡くなったピアニストの中村紘子さんが提唱した「浜松国際ピアノコンクール」がそのモデルのようです。) 登場するピアニストは天才というほかはない16才の日本人男性、幼いころから将来を嘱望されたが挫折し、ここで復活を期す20才の日本人女性、その女性と幼いころ一緒にピアノを学んだ同年齢のアメリカ人男性(国籍はアメリカでジュリアード音楽院に籍を置いていますが、これまでヨーロッパ各地で生活)、プロのピアニストにはならず企業に勤務しているものの、再び音楽の真髄に迫ってみることを決意した28才の男性です。 これらの登場人物が、1次、2次、3次、ファイナルの審査に臨む状況を出場するピアニストの立ち位置から、あるいは審査員の立ち位置から描くもので、とても読みごたえのある小説でした。 この小説で作者が描きたかったことは音楽の神秘、それを奏でるピアニストの感性や宇宙観のようなもの、音楽と自然との関係、それらすべてを具現する人間のすごさということだったと思います。音楽の専門家ではない小説家の恩田陸のこの小説での筆力には感動させられました。 音楽も文学もその他あらゆる芸術の力はすごいですね。人間に歓びや深い感動を与えてくれます。 |