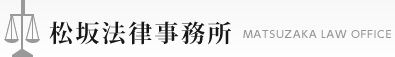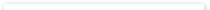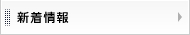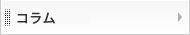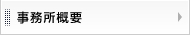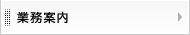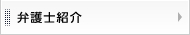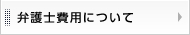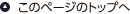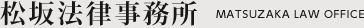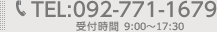- ホーム >
- コラム
| 2021/09/02 | 弁護士松坂徹也のコラム(46)「地に足をつける」 |
今、我々人類につきつけられている課題は、気候変動をどうするか、人間とウイルスとの関係をどう考えるかです。とても重い課題です。これらの問題は、小手先の対応で解決できるようなものではなく、どちらも地球環境意識のもと、これまでの人類の来し方を振り返りながら、そして行く末を考えながら解決していかなければならないということだと思います。なぜならこの2つには共通している地球規模の課題があるからです。 世の中の多くの人の問題意識に、コロナにどう打ち勝つかとか、そのための武器がワクチンであり、それさえ打てばいいとか、気候変動(危機)問題については脱炭素とか、その割合目標をどうたてるか、SDGsにどう取り組むかとかいうものがあります。果たしてこのような考え方による対応でいいのでしょうか。この問題には、地球環境の収容力は有限であることを意識したうえで地球規模で考え、対応しなくてはなりません。要するに、地にしっかり足をつけて考えなければならないということです。今回はこのような観点からの問題提起です。 この地に足をつけるということには、まさに大地、地球環境をじっくりとみつめながら日々を生きていくということ、そして深く考えることなく世の中の流れに安易に乗っていくということをあらためなくてはならないことにあります。 地球では人間による、人間だけの利益のための開発が世界中のいたるところで行われ、これによって自然が破壊されています。これが気候変動の要因になっていますが、この自然破壊はそれだけではなくこれまで人間と無縁であったウイルスと人間との関係に大きな変化をもたらしています。人間とウイルスとの適正な距離がおかしくなってきたのです。今回の新型コロナウイルス感染もそこにあると言われています。気候変動によりシベリア凍土の氷がとけていますが、そのうちこれまでその中にあって眠っていたウイルスが活動をはじめ、人間に近づいてくるのではという危惧もあります。 地球上ではウイルスは人類より先住ですから人間の行動が静かに眠っていたウイルスを起こすことになる事態にもなるのでしょう。 このように考えると、気候変動問題と新型ウイルス問題は密接に結びついているということになり、この2つの問題に対する対策はつなげて考えなくてはなりません。そのようにすることが地に足のついた考えということになるのではないでしょうか。 そのような観点に立ってみますと、ワクチンを武器にしてウイルスに打ち勝つという考え方は本質が見れていないと言わざるを得ません。これまでの科学的知見の蓄積と今後のさらなる研究によってある程度の成果は期待できるのでしょうが、人間は地球最強のウイルスを克服することはできないでしょう。ワクチン等の武器を使ってこれに勝つ、これを打ちのめすなどということはありえないことです。高度な科学的知見をもつ人間は万能であるという傲慢な考え方をすて、もっと謙虚になって地球のあらゆる生物、自然に対し畏敬の念を持つことだと思います。 SDGs(持続可能な開発目標)のなかには、自然環境、気候を守ろうというものがあります。これはこれで意味のある行動なのですが、それにあたっては上記のような考え方を基本に据えておく必要があります。そうしないと地に足がついた活動にはなりませんから。 例えばペットボトルやレジ袋の問題、それが存在し続けることを前提に単に量を減らそうとする取り組みは地に足がついているとは言えません。問題の本質はそれらが多量に消費される世の中でいいのかということです。 『人新世の資本論』の著者、斎藤幸平氏(経済思想家で大阪市立大学大学院准教授)は同著書のなかで「使用価値」と「価値」を区別し、「使用価値」が生活に必要なものの価値、「価値」は商品価値すなわち商品として売り出すことによって儲けが出る価値と定義しています。水を例にしますと、水は人間にとって最も使用価値は高いが、日本では水はどこにもありますから、お金を払って買うというものではありません。ですから、水は本来商品としての価値はありません。水は「使用価値」はあっても「価値」はないというものです。ところが、最近は「価値」があるものとして考えられています。ペットボトルに入れられて、そして多くの市民がそれがおいしい、体にいいと思ってお金を出して買う。このペットボトルに入っている水を自由にたくさん買うためにはお金がいる、お金をたくさん稼ぐため長時間労働をする、そしてこの長時間労働によってCO₂の排出量が増え、地球環境の悪化、気候変動をまねく。このように物事を考えますと、人間はこれからどう生きるべきかがみえてきます。水の「価値」化をテーマにした映画があります。ロマン・ポランスキー監督、ジャック・ニコルソン、フェイ・ダナウェイ主演のアメリカ映画「チャイナタウン」という1974年に制作された映画です。時代設定は1930年代ですが、ロサンゼルスの水不足が深刻化した時代の水の利権に絡むドラマです。この映画は、水を利権の対象とした醜い争いを描いた映画です。多くの映画賞をとった作品ですからご覧になった方も多いと思いますが、何でも利権、ビジネスの対象とする人間の愚かさが描かれています。あらためてこの映画をみることによって、生活に大切なものはお金ではない、お金は人間を狂わせることがあるということを感じさせられました。故中村哲さんが主宰されていた「ペシャワール会」はアフガニスタンに用水路を建設して水を提供し、同国人に多くの幸福が生まれましたが、そこにはビジネス的なものは何も入っていません、このことは全く逆の発想です。 SDGsの取り組みは素晴らしいですが、物事の本質をとらえた活動にならなければならないと思います。 ウイルスに話を戻しますと、限りなき成長を求め続けると、次々と新種のウイルスが人類の前に現れますし、地球環境の破壊、気候変動、気候危機は増して続くでしょう。このような観点に立って物事を考える必要があると思います。この視点こそ「地(球)に足をつける」ということではないでしょうか。 コロナ感染が爆発的となった状況のなか、オリンピックを開催したことは「地に足がついていない」象徴のようなものと言えるでしょう。又、ワクチン接種はそのウイルスへ向けたその場だけの対応にすぎませんから、ワクチンですべて解決と考えていたのでは次から次に出てくる新たなウイルスの発生に対して後手後手にまわるだけです。コロナに打ち勝つとか、ワクチンがコロナと戦う武器になるなどと言っていたのでは本質的な解決には至りません。この問題については、今しっかりとした考え方を確立して取り組まないと人類の将来は真っ暗だと思います。地に足をつけた生活をすることこそ、コロナ終息への道、気候正義への道になると思います。復興五輪とは名ばかりの東京オリンピック開催へ向けた再開発、東京の街づくりも地に足がついているとは思えません。東京と復興の対象であるはずの東北との格差を広げるばかりで、東北から人や物を集奪する都市づくりと言えるでしょう。これまでの東京と東北との関係は、東北が東京を支えてきた、東北の犠牲のもとに東京の発展があったというものでした。このことは、福島原発によって電力の供給を受けるのは東北の人達ではなく、東京にいる人達や企業であることからもわかります。今回のオリンピックも同じことです。「風とともに去りぬ」という古いアメリカ映画があります。1936年制作の大作で、ヴィヴィアン・リー演じるスカーレット・オハラとクラーク・ゲーブル演じるレット・バトラーがあまりにも有名ですが、私が観た映画でのオハラ家の会話、その中で召使いが話す言葉の日本語字幕は東北弁となっていました。このことに違和感を憶えたことを記憶しています。 コロナ禍を機に東京重視から地方回帰へ向かう槌音が聞こえてくることを願うばかりです。それが実現できれば、変わることなく昔のまま残っている東京の良さも再発見できるでしょう。東京には江戸時代の各藩の緑豊かな江戸屋敷があって大きく変わることなく今でも残っていますし、下町にも江戸時代の風情を残したところがあります。 |